エンジンの内径(ボア)と行程(ストローク)の比率は、エンジンの特性に大きな影響を与えます。この記事では、ボアとストロークとは何か、その比率(ボアストローク比)によって分類されるエンジンの特徴と違いについて詳しく解説し、それぞれの使用シーンに適した車種の例を紹介します。
内径(ボア)と行程(ストローク)とは
- ボア:シリンダーの内径
- ストローク:ピストンが上下する距離
ボアストローク比は「ボア÷ストローク」で計算され、エンジンの特性を決定する重要な要素です。
ボアストローク比によるエンジンの分類
ショートストロークエンジン(オーバースクエアエンジン)
内径が行程よりも大きい場合、ショートストロークエンジンと呼ばれます(ボアストローク比>1)。このタイプのエンジンは高回転型で、スポーティな走行性能を持ちます。エンジンの高回転域での出力が高く、レスポンスが良いのが特徴です。そのため、スポーツカーや高性能車に多く採用されています。
- 使用シーン: 高速道路やサーキット走行に向いています。高回転域でのパワーが求められる場面で真価を発揮します。
- 車種の例:
- ポルシェ 911ターボ (3.8L水平対向6気筒DOHCターボ): ボアストローク比 = 1.33 (ボア102.0mm、ストローク76.4mm)

- マクラーレン 570S (M838TE型3.8LV8DOHCターボ): ボアストローク比 = 1.33 (ボア93.0mm、ストローク69.9mm)

- フェラーリ 488 GTB (3.9L V8ターボ): ボアストローク比 = 1.04 (ボア86.5mm、ストローク83.0mm)

- 日産 フーガハイブリッド (VQ35HRエンジン): ボアストローク比 = 1.17 (ボア95.5mm、ストローク81.4mm)
ロングストロークエンジン(アンダースクエアエンジン)
内径が行程よりも小さい場合、ロングストロークエンジンと呼ばれます。このタイプのエンジンは低回転域でのトルクが高く、燃費が良いのが特徴です。エンジンの回転数を上げずに大きな力を発揮できるため、トラックやSUV、実用車に多く採用されています。
- 使用シーン: 街乗りや低速走行が多い場面に向いています。信号待ちや渋滞が多い都市部での運転がスムーズです。
- 車種の例:
- 日産・ノートe-POWER: HR12DE型エンジン(ボア:78.0mm、ストローク:83.6mm、ボアストローク比:0.93)
- トヨタ・アクア: 1NZ-FXE型エンジン(ボア:75.0mm、ストローク:84.7mm、ボアストローク比:0.88)
- ホンダ・フィット: LEB型エンジン(ボア:73.0mm、ストローク:95.0mm、ボアストローク比:0.77)
スクエアエンジン
内径と行程がほぼ同じ場合、スクエアエンジンと呼ばれます。このタイプのエンジンは出力とトルクのバランスが良く、全体的にバランスの取れた性能を発揮します。そのため、多くの一般的な乗用車に採用されることが多いです。
- 使用シーン: 街乗りから高速走行まで幅広く対応できます。バランスの取れた性能が求められる場面で活躍します。
- 車種の例:
- ホンダ シビックType R: K20C型エンジン(ボア:86.0mm、ストローク:86.0mm、ボアストローク比:1.0)
- ホンダ S2000: F20C型エンジン(ボア:86.0mm、ストローク:86.0mm、ボアストローク比:1.0)
- トヨタ 86: FA20型エンジン(ボア:86.0mm、ストローク:86.0mm、ボアストローク比:1.0)
- スバル BRZ: FA20型エンジン(ボア:86.0mm、ストローク:86.0mm、ボアストローク比:1.0)
最適なボアストローク比は?
結局のところ最適なボアストローク比はいくつなのでしょうか?
最適なボアストローク比は、エンジンの用途や求める性能によって異なります。一般的なガソリンエンジンではボアストローク比が1.0(スクエア)付近、もしくはややロングストローク寄りに設定されることが多いです。これは、バランスの取れた出力特性と耐久性、扱いやすさを重視した設計です。
一方で、高回転・高出力を狙うスポーツカーやレース用エンジンでは、ショートストローク(ボアストローク比<1)が採用される傾向があります。たとえば、F1エンジンではボアストローク比が0.65前後と極端にショートストローク化されており、最高回転数や出力を優先しています。
逆に、燃費やトルク重視のディーゼルエンジンや大型船舶用エンジンでは、ロングストローク(ボアストローク比>1)が選ばれています。これは、低中回転域でのトルクや燃費性能を重視するためです。
まとめると、「最適」なボアストローク比は用途によって異なり、一般的な乗用車やバイクなら1.0前後、高回転・高出力重視なら1未満、トルクや燃費重視なら1より大きい値が選ばれるのが主流です。
よって、用途によってエンジンに求める特性や使い方に合わせて、最適なボアストローク比を選択するのが理想的です。
まとめ
エンジンの内径と行程の比率は、その特性や用途に大きな影響を与えます。ショートストロークエンジンは高回転型でスポーティな走行性能を持ち、ロングストロークエンジンは低回転域でのトルクが高く燃費が良いです。スクエアエンジンは出力とトルクのバランスが良く、全体的にバランスの取れた性能を発揮します。設計者は、車両の用途や目的に応じて適切なボアストローク比を選択しており、どのタイプが最適かは、車両の目的や使用環境によって異なります。
これらの特性を理解することで、各車種のエンジン設計の意図や、その車両が得意とする走行シーンをより深く理解することができるでしょう。新車中古車をお探しの際も、ぜひエンジンの仕様を確認してご検討されてみると、メーカーごとのその車に込められた思いが見えてくるかもしれません。
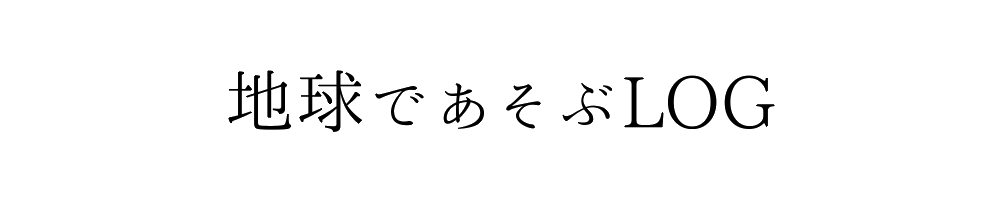



コメント